|
こんばんは! 本日は夜開催のミューケン・シップ。 続々と集まる乗組員たちはちょっと緊張気味。 だって今日はミュージカル界のレジェンドにおはなしを伺うんですものッ! そう、本日のゲストは東宝のプロデューサー、宮崎紀夫さん。 ミューケン・シップ2018開講のご案内の後に急遽登壇が決まったというエピソードまで伝説級の宮崎さんなので、一体どんなおはなしが飛び出すのか、乗組員みんなでそれはそれは楽しみにしていたのです。 実際お会いしてみると、宮崎さんはとても穏やかで、はんなりやわらかい印象の方。 キャリア55年(!)の敏腕プロデューサーということだったので、もっと怖い方なのかと思っていました。 そしていわゆるプロデューサー巻きもしていらっしゃいません!笑 宮崎さんは1963年(昭和38年)に東宝株式会社に入社してから、その長いキャリアのなかで数えきれないほどの作品に携わっていらっしゃいます。 それぞれの作品の上演回数で言えば延べ1万回を超えるんですって! 宮崎さんが入社したころ、演劇界でどういうことが起こっていたのかご紹介すると… 1963年に演劇界でおこったこと
宮崎さんと日生劇場とキャリアの長さが同じとは・・・。 まさに日本のミュージカルの歴史の証人ということがわかります。 東宝に入社してからの宮崎さんは、演出部に所属して修行の毎日を過ごします。 当時は舞台のことについては何でもわかるようになるため、小道具、大道具、衣装、音楽など、ひとりで何役もこなしたそうです。 前述した「マイ・フェア・レディ」初演の際には宮崎さんは舞台監督助手を担当。 菊田先生、スタッフとキャストが一丸となって邁進した結果、マイ・フェア・レディの上演は大成功。 101人(!)のキャストによる豪華な舞台は観客に大ウケで、追い出しの音楽が終わっても、スタンディングオベーションの嵐で観客たちは全く帰ろうとしなかったのだとか。 その日の夜、『やっぱりおれはミュージカルでやる!!』と決意した宮崎さん。 それが東宝の敏腕プロデューサーとしての道を突き進む第1日目となったのでした。 そんな宮崎さんにご自身が影響を受けた方をお聞きすると、こんなふたりのお名前が出てきました。
小林一三さんは阪急電鉄の創始者でありながら、宝塚歌劇をつくり、東宝の初代社長を務めた方。 たくさんの名言を残していらっしゃり、宝塚歌劇のモットーである”清く正しく美しく”はあまりにも有名ですよね。 小林先生は、”高尚な娯楽本位の国民劇”をつくりたいという信念をもちつづけ、年に4回もニューヨークに渡り本場のミュージカルを見て勉強をなさったのだそうです。 菊田一夫さんは、戦後のミュージカルの立役者。 ミュージカル「マイ・フェア・レディ」の上演権を獲得し、日本で始めて”舶来モノ”の作品を上演して成功させただけでなく、その後も数々のヒット作品を世に送り込んだ方なのだそうです。 (「菊田一夫賞」でそのお名前を聞いたことがある方も多いかもしれませんね^^ ) 宮崎さんが影響を受けた小林先生と菊田先生に共通するのは、強い信念を持ち、その実現に向けて努力し続けたところかもしれません。 そして、宮崎さんがふたりの遺志を継ぎ、人生をかけて日本におけるミュージカル文化の興隆に寄与していらっしゃったということですか・・・! く~~~~~~震える!!! 目の前で語られる物語と登場人物の豪華さにおどろきの色を隠せない乗組員たち。 塩ちゃん先生も思わず、『宮崎さんのおはなしでミュージカル作品が作れそうですね』とポロリおっしゃっていました。 わっ!その作品、ぜひ観たいです! ところで、宮崎さんのお仕事である、プロデューサーってどんなことをするのかご存知でしょうか。 プロデューサーとは 作品制作における最高責任者。 企画、予算管理、海外作品の権利者との折衝、役者のキャスティング、スタッフの人事権等、作品にまつわる全ての責任を負う。 プロデューサーの仕事は宮崎さんにとって辛いことのほうが多く、お客様の喜ぶ顔を励みにがんばっていたんです、とにっこりする宮崎さん。 意外だったのは、プロデューサーはスタッフの間に入って調整することが多いため、結構中間管理職的な役割なんですよとおっしゃっていたこと。 華やかに見えても、本当に大変なお仕事なのでしょうね。。。 「座組(カンパニー)はファミリーだから気持ちをひとつにして作品を作り上げなければいいものはできない」と断言する宮崎さんのあたたかく柔らかいお人柄があってこそ、長きにわたって個性豊かなキャストやスタッフをまとめあげてこれたのだなと感じました。 宮崎さんと塩ちゃん先生は30年以上あらゆる作品でタッグを組んでいらっしゃいます。 ミュージカルで大切なのは脚本と音楽なので、音楽監督と指揮者を誰にお願いするかは超重要! 我らが塩ちゃん先生は売れっ子でいつも取り合いなので、宮崎さんは、作品が決まったとたんにまず塩ちゃん先生のスケジュールをおさえるんだとか。 とくに「ラ・カージュ」は客席参加の場面が多くあるため、コミュニケーションをとるのが上手な塩ちゃん先生が必要なんですって! 塩ちゃん先生にとっても「ラ・カージュ」は大好きな作品なんだそうで、歌・ダンス・笑いのなかに、切なさ・はかなさがちりばめられていて、人を信じることの大切さを教えてくれる素晴らしい作品だと大絶賛。 東宝が長い間大切にしてきた宝石のような作品ですし、これは俄然観劇が楽しみになってきました。 これだけたくさんの経験を積み、数々の作品に携わってきた宮崎さんでも、”日本発オリジナルミュージカル”に関しては悔いが残っているのだそう。 これからは若い人のために橋渡しをしたいと微笑む宮崎さんの目がやさしくてやさしくて、なんだかウルっときてしまいました。 宮崎さんが、小林先生や菊田先生の夢を受け継いだように、宮崎さんの夢も誰かが繋いでくれますように。 ミュージカルにまつわる素敵なおはなしをたくさん聞いて、ふわふわとした足取りで帰っていく乗組員たち。
次回はいよいよ塩ちゃん先生のご専門である、ミュージカルの音楽についてのおはなしを伺います。 ゲストはピアニストの国井雅美さん、パーカッショニストの長谷川友紀さん&麻紀さん姉妹です。 どうぞおたのしみに!^^
1 Comment
おはようございます! ミューケン・シップ、第5回目の朝です。 3月も中旬に入り、早朝でもずいぶん明るくなってきました。 乗組員のみなさんは、ラ・カージュ・オ・フォールの観劇チケットのくじびきを引きながら乗船です。 お隣の人は誰かな。どきどき。 今朝のゲスト講師は振付師の萩原季里(はぎわら きり)さん。 ラ・カージュ・オ・フォールでは振付助手をご担当されています。 スラっとスタイルがよく、ピシっと背筋が伸びて、ひとつひとつの所作が美しい季里さん。 なんてカッコいい・・・。 季里さんはラ・カージュ・オ・フォールにはもともとはキャストとして出演されていらっしゃいましたが、振付のお仕事をするようになったのだとか。 塩ちゃん先生とは長年チームを組んでいらっしゃり、初めての仕事は「ラ・マンチャの男」だったとのこと。 目を見ればお互いの考えていることがわかる、みたいなお二人の間の空気感いいなぁ。 さて、季里さんは”振付助手”として振付の方のアシスタントを務めていらっしゃいますが、振付助手の一番大切な仕事は”振り起こし”。 作品の中での役者たちの動きは全て振付として決められているのですが、そのひとつひとつを確認していく作業が”振り起こし”だそうです。 とくにラ・カージュ・オ・フォールはダンスシーンが多いため、振り起こしをするのには6ヶ月(!)もかかったんですって! また、振付と音楽は切っても切れない関係なので、塩ちゃん先生とは逐一相談しながら作品作りを進めるのだそうです。 季里さん曰く、塩ちゃん先生は振付を活かす音作りのセンスが素晴らしく、いつも役者さんたちがやりやすいように作ってくださると絶賛していらっしゃいました。 季里さんの仕事は身体が資本。 ダンスの技術を磨くことも重要ですが、メンテナンスが何よりも大切であることに気づいてから、日本ではまだあまり知られていない”ヤムナメソッド”というセルフボディケア法をいち早く取り入れ、強くしなやかな身体作りを実践されているのだそうです。 ついにはインストラクターとしての資格もとって、活躍の幅をひろげられていらっしゃるのだとか。 やはり素敵なスタイルは努力の賜物なのですね・・・。反省。 というわけで、季里さんにオフィスでもできる簡単なストレッチを教わっちゃいました。 片方の鎖骨を両手でロックして、手と反対に頭を傾け、目線をあさっての方向に送ります。 むーーーーーーん! おぉ、なんだか肩まわりがスッキリした感じ! 毎公演立ちっぱなしで指揮をする塩ちゃん先生も積極的にエクササイズに参加されました。 次に、みんなでミュージカルウォーク! 両手を広げて、おへそは正面に向けたまま横歩き。 ぞろぞろ〜〜ぞろぞろ〜〜 背筋が自然とピッと伸びて、ミュージカルスターになった気分になれました♪ 最後にクラスを3つのパートに分けて、声を出しながら違うリズムを手拍子することに。 むむむむ難しい〜〜 なかなか手拍子が揃いません。 見かねた塩ちゃん先生、ついついお仕事モードのスイッチが入り、指揮を振って丁寧に教えてくださいました♪ なんという贅沢! 塩ちゃん先生の熱血指導の成果か、乗組員の手拍子もバッチリ揃い、塩ちゃん先生に合格点をいただきました。 ホッ。 楽しい話を聞いたり、朝から体を動かしたりしていると1時間があっという間。
乗組員はウキウキした気分で朝の有楽町に消えていきました。 次回はいよいよレジェンドと言われる東宝プロデューサー、宮崎紀夫さんの登場です。 どうぞお楽しみに! こんにちは! 今日はいよいよ観劇DAYです。 ミューケン・シップ乗組員みんなで観るのは、ご存知「ジキル&ハイド」。 2001年の初演以来何度も上演されているミュージカルファンにとってはお馴染みの作品です。 塩ちゃん先生がたびたびミューケンシップのクラスでジキル&ハイドの素晴らしさについて話していただいていましたので、乗組員みんな興奮を抑えきれません。ワクワク。 会場は東京国際フォーラム ホールC。 この会場の壁や手すりには花梨材がふんだんにあしらわれているため、ラグジュアリー感満載。空気にぬくもりと湿度があるので、席につくなり深呼吸したくなっちゃうような居心地の良さなんです。 仕事に忙殺されている日常から離れ、華やかで夢のようなひとときを過ごすにはぴったりなところなんですよね♪ ミューケン・シップの乗組員たちは2階の舞台全体を見下ろせる席に陣取って、開演前にもかかわらずオペラグラスを覗きながらニヤニヤ。 だってオーケストラピットの中にいらっしゃる我らが塩ちゃん先生がよく見えるのですもの! お仕事モードの塩ちゃん先生、すてきです! そして開演を伝えるアナウンスが流れ、幕が開きます! 観劇後の気持ちをたとえるならば、熟練のシェフが上質の素材を使い見事な手仕事で仕上げたフレンチのフルコースを堪能した後の感覚とでも言いましょうか。(作品の舞台はイギリス・ロンドンなのですが。汗) 「上質な素材」のなかでもずば抜けて素晴らしいのは楽曲でしょう。 稀代のメロディメーカーであるフランク・ワイルドホーンが華々しいデビューを飾った作品だけあって、パワフルでぐわっと心を鷲掴みにされる曲ばかり。 有名な「This is the moment(時は来た)」だけでなく、「Take me as I am(ありのままの)」、「Someone like you(あんなひとが)」、「Murder, murder!(事件、事件)」、「Dangerous game(罪な遊戯)」などどこをとっても名曲ぞろい。 ワイルドホーンの曲ってちょっと中毒性すらあるものが多いのですが、このジキル&ハイドに関してはどの曲も耳に残って脳内で鳴り止まなくなるんです。 乗組員たちが観劇した2階席からはアンサンブルキャストの動きの美しさや照明ワークの巧みさもよくわかり、見ごたえ聴きごたえたっぷりの3時間でした。 将来、自分のライフステージが変わってからこの作品を再度観るときの印象の変化も楽しんでいきたいなぁ。 終演後、塩ちゃん先生とパーカッション担当の長谷川友紀さん麻紀さん姉妹がロビーに出てきてくださり、作品の解説をしてくださいました。 キャスト・スタッフ全員がこの作品が大好きで誇りを持って仕事をしているということ、ワイルドホーンさんの楽曲構成が役の気持ちの変化に密接にリンクしていること、ジキル&ハイドの曲はどれもドラムスのハイハットシンバルなどで拍子を刻まないのでオーケストラプレイヤーたちが息を合わせて演奏する必要があること・・・などなど裏話に一同ため息。 友紀さん&麻紀さんはオーケストラピットの中でふたり折り重なるようにしてアクティブに演奏していらっしゃいましたが、非常にタイミングがシビアな場面では姉妹のあうんの呼吸がものを言うんですって! 「そういえば、お姉さんがシンバルを叩いている一方で、妹さんがその響きを止めている瞬間を目撃した!」という乗組員のコメントに、よくわかりましたねと思わず拍手する長谷川姉妹。 わー!そんな瞬間があったとは!ジキハイ、俄然また観たいです! 帰り道、ジキル&ハイドの名曲たちを口ずさみながら、改めてミュージカルってキャスト、オーケストラ、舞台スタッフの皆さんが作り上げる総合芸術なんだなぁと実感。
奥深いミュージカルの世界、もっと知りたい欲求がふつふつと沸いてきました! 次回のクラスも楽しみです^^ |
Authorむらかみちあき ArchivesCategories |
OPERATED BYSUPPORTERS |
丸の内朝大学ミューケンシップ |
プライバシーポリシー
|




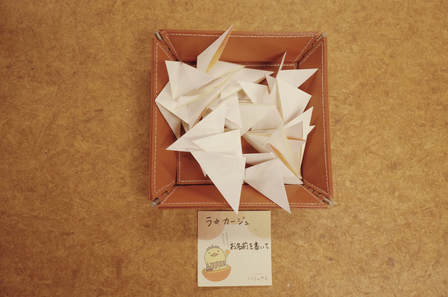











 RSS Feed
RSS Feed